歩けるようになり、行動が活発になってきた1歳児。じっとしていられないので外に行きたがることも多く、公園や児童館などに出かけることも多くなるでしょう。出かけることができない日はいたずらばっかりで困っていませんか?できることも限られているのでお家遊びもマンネリ化してしまいがち。そこで今回は、楽しく過ごせる1歳児の室内遊びを紹介します。準備なしで手軽にできて発達にも繋がるので是非試してみて下さいね☆
1.お絵描き

紙とクレヨンがあればできるお絵描き。このお絵描き一つとっても、子どもの発達に重要な要素がたくさん含まれています。クレヨンがうまく持てなくたっていいんです。「持つ」「握る」という動作こそ、手先・指先の発達を促します。クレヨンで描くとき、力いっぱい書けば濃い線、弱い力で書けば薄い線になりますよね。力を入れすぎるとクレヨンが折れることもあります。力加減を調節することにも繋がります。
お絵描き一つで「持つ」「握る」「動かす」「書く」「調節する」ことを覚えるんです。また、いろいろな色の中から好きな色を選んで自由に描くことで「表現する」ことの楽しさも覚えます。なぐり書きでもいいんです。たくさん褒めてあげて下さいね。クレヨンは、色を覚える・識別するのにも欠かせないアイテムです。
2.パズル

パズルといってもこの頃にできるのは、かたち合わせです。これを通して、限られた空間に「当てはめる」こと、ものには「形」があることを覚えます。パズルを持って当てはめるという手先・指先の動作も重要ですよ。頭と指先の運動ができるなんて一石二鳥ですね。
3.積み木
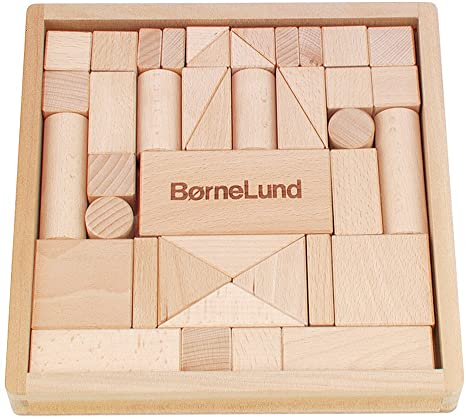
積み木遊びも手先・指先の発達には大切なアイテム。この時期は、積み木で何か作るというより、「積む」「並べる」ことの多い時期です。これもまた発達には欠かせない動作です。同じ色や形を集めたりして、色や形の認識も促すことができます。
4.粘土

粘土は、感触や形の変化を楽しむことができます。1歳児には丸めたり、伸ばしたりという作業も難しかったりしますが、指で「つつく」「ちぎる」ことは指先の発達を促し、脳の活性化に繋がります。1歳児だとなんでも口にいれてしまうので不安がありますが、そんな時は口に入れても安全なお米粘土や小麦粉粘土がおすすめです。お米粘土は安価で手に入りやすく、最近では100均でも販売されていますよ。
お家に粘土がない場合でも小麦粉粘土なら家にあるもので作ることができます。アレルギーの心配な方や長期間楽しみたい方は、寒天粘土もおすすめです。いろいろな粘土に触れてみるのも感触の違いを知るいい機会になりますよ。
5.ごっこ遊び

おままごと
お世話ごっこ
6.運動遊び

お山遊び
ボール遊び
7.新聞遊び
ビリビリ遊び

その名の通り新聞をビリビリ破って楽しみます。思う存分思いっきり新聞を破ることは子どものストレス発散にも繋がります。その中で「ビリビリ」と破れる音が聴覚を刺激し、「ちぎる」という指先の運動にも繋がります。ちぎる大きさもだんだんと細かくしていくことで、手先も器用になるはず!!
ボール遊び(玉入れ)

新聞紙をぐしゃぐしゃと丸めてボールを作ります。一見簡単そうなボール作りですが、経験のない1歳児はまだまだうまく丸めることができません。丸める練習をしながら、脳を刺激しましょう。できたボールは投げて遊んでもいいですし、カゴを置いておいて玉入れのようにして遊ぶのもオススメです。新聞を破る時もそうですが、新聞を丸める時の音にも耳を傾けてみましょう。
新聞シャワー

こちらは①の延長で遊びます。ビリビリと破いた新聞をかき集めて上に投げます。シャワーのように降ってくる新聞に子どもは大喜び!
お風呂
8.段ボール遊び

お家
トンネル
乗り物
9.工作

道具を使って作るのはまだまだ難しいので、ママが作ったものにシールやスタンプで飾り付けをしてみましょう。シールを剥がしたり貼ったりするのも指先がおぼつかない1歳児にとっては難関。細かい作業をすることは、指先を使う練習にもなります。
くっつく面とくっつかない面があることも知らせていきましょう。スタンプを「押す」というのも力加減が重要になってきます。そして何より大切なのは、できたという「達成感」を味わうこと。「できたね」とたくさん認め、できた喜びを感じられるようにしましょう。
10.知育

いろいろな知育おもちゃも売られていますが、ママが作ってあげられる知育おもちゃもたくさんあります。ネットで調べるとたくさん出てくるので余裕のある方は参考にしてみてくださいね。作るのはちょっと・・・というママもいると思いますが、ティッシュの空き箱にガーゼを繋げたものを入れるだけでも立派な知育おもちゃ。いたずら盛りのお子さんがティッシュを出してしまう経験をしたことがある方も多いと思いますが、これにも「摘まむ」「出す」「引っ張る」「入れる」「片付ける」というたくさんの動作が含まれているので知育に繋がるんですよ。
また、知育おもちゃがなくてもジャンバーやポーチなどチャックのついたものを与えるだけでもお子さんにとってはおもちゃとなり、チャックを通して「開ける」「閉める」ことを覚えます。マヨネーズの空き容器でも「潰す」「ふくらます」ことを覚え、空気が出ることを楽しみます。かばんや袋を与えれば、「入れる」「運ぶ」ことを覚え、身近にあるものを入れて持ち歩きます。電卓を与えれば、ボタンを「押す」ことを覚え、数字が出てくることを楽しみます。
このように日常にある身近なものにも知育に繋がるものはたくさんありますよ。
11.ふれあい遊び
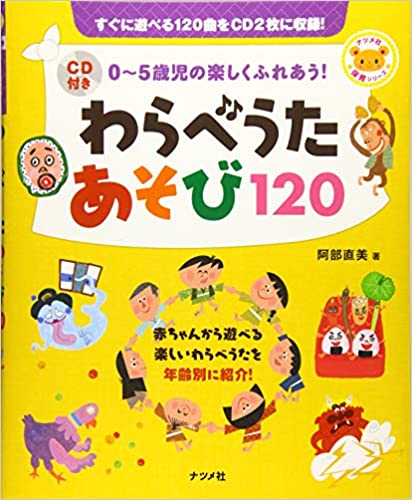
童歌(わらべうた)
ひこうき
歩けたり話せるようになるだけで、遊びの幅がぐんと広がります。日中は家にいないパパにとっても遊びやすく感じるのではないでしょうか?せっかく遊ぶなら発達を促すものを・・・と思われるかもしれませんが、この時期は意外と何をしても発達に繋がります。「パパやママと遊ぶ」ということが何より大切なんですよ。
最終更新日 2025年3月2日



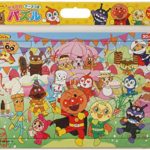







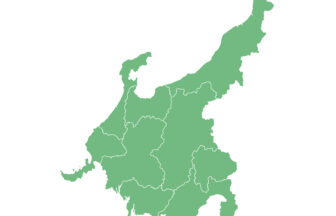




















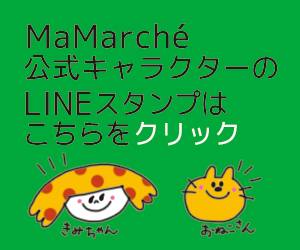



この記事へのコメントはありません。